こんにちは。ストレスとおさらばしたいと思っている佐々井と申します。
今回、ご紹介するのは、日本ECサービス株式会社代表取締役の清水将平さん著・「ストレスレスの授業(レッスン)」です。
副題は『「ものさし」を変えれば悩みは悩みではなくなる』。
著者の清水将平さんは、現在のいわゆる会社経営者になるまで、14回の転職を経験されています。
日本人の平均転職回数は2~3回と言われていますので、平均以上の転職経験と、それにまつわるストレス体験をお持ちになっておられます。
著者自身も、それを自認されており、ある職場ではストレスのあまり、うつ状態になったこともあったそうです。
そうした体験の末、「ストレスをストレスと感じなくなる方法」を会得したという著者。
要点は「見方や考え方を変えること」です。
本書のタイトルにある「ものさし」とは、「見方・考え方」のことなんですね。
本書をオススメしたい方はこちら。
それでは、本書の内容についてご紹介していきます。
総論:「ものさし」を変えることで減らせるストレスは5つ
人がそれぞれ持っている「見方や考え方」=「心のものさし」の単位・基準は多種多様です。
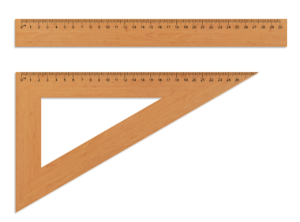
例えば…
・責任の所在は「他人」か「自分」か
・相手との「接点」「共通要素」はあるかないか
・視点が「ミクロ」か「マクロ」か
・価値観が「日本のもの」か「世界のもの」か
・人生は「誰のもの」か

こういった、「ものさしの基準」を変えることで、ストレスの多くはストレスではなくなってくるそうです。
では、その減らせるストレスとはなにか?
それは、5つあります。
「仕事」「人間関係」「お金」「健康」「夢」の5つです。

それでは、次項から、そのストレス対処について紹介していきます。
対「仕事」のストレス
「仕事」のストレスを抱え込まないためには、まずは「ボール」を持たないことです。
ボールとは、「仕事の案件」のことです。

仕事で関わる「お客様」「相手方」「チームのメンバー」は、当然ですが、「他人」です。
「他人」であるからには、「自分」と全く違う人間なので、得手・不得手・仕事のペース・価値観などなども異なります。
まずは、ここを認識し、なんでも「自分基準」のものさしでも見ないことですね。

「仕事の案件」も、人によって向き・不向きもあります。
その仕事に「向いた人・得意な人」に、仕事を振ることができればトータルの効率は上がりますし、ボールを預けても良いのではないでしょうか。
ただし、「責任は自分のもの」と捉えましょう。
「失敗したら自分の責任だ。こんな自分はダメだ!」という「自分を責める」ことではありません。
「自分に責任があり、もっとこうすればよかったのでは?」という視点を持とう、ということです。

次に、仕事の手段・手法もフレキシブルに行きましょう。
例えば、メールへの回答がメールでなければならない、とは限りません。
仕事に「権威性」が必要とあらば、上司や先輩にお出ましいただくことも考えましょう。
使えるものは有効に活用して、自分の手持ちのボールを減らしましょう。

また、「相手のものさし」も考えましょう。
例えば、相手から仕事を依頼されたとき、
「今日中にしなきゃいけないんですか?」
と
「今日中にした方がいいですか?」
とでは、相手と自分の双方にかかるストレスが変わってきます。
前者では、「強制・不服」のように聞こえ、後者は「確認・要望」のように認識できます。
「マスト(~でなければならない)」より「ウォント(~したい)」を口ぐせにしたいものです。

対「人間関係」のストレス
「人間関係」については、まず「嫌い」という基準を無くしましょう。

「人間関係」にも「2:6:2の法則」があるといい、「10人のうち2人は好き、6人は普通、残り2人は嫌い」になるそうです。
この「残りの嫌いな2人」を「嫌い」ではなく「どうでもいい」に変えてしまい、ビジネスライクに行きましょう。

また、「嫌い」「ダメだ」といったネガティブ言葉を口にするのも控えましょう。
Aさんについて、あなたが「嫌い」だとしても、あなたの知人は「好き」かもしれません。
そこで、あなたが「Aさんが嫌い」と言ったとすると、知人はストレスを感じることでしょう。
自分の交流範囲を狭めないためにも、ネガティブ言葉は禁物です。
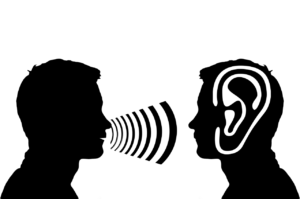
また、「起きてしまった事実」や「悩み」で、自分がコントロールできないことに、イライラしても仕方がありません。
自分がコントロールできないことに意識を向けるよりも、コントロールできることにフォーカスしましょう。
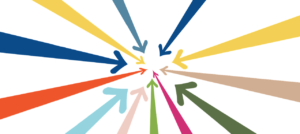
また、人生の先輩たる「親や上司」の言うことが、いつも正しいとも限りません。
何事にも「真正面から向き合う」必要なく、自分の心を守りながら受け流していく、ということも必要になります。

対「お金」のストレス
サラリーマンの意識として、「お給料は貰うもの・時を経ると上がるもの」というものがあるかもしれません。
そこは、「お給料は稼ぐもの・上げるもの」と考え方を変えましょう。

「いや、給料の時給って決まってるし!」という方。
今のご時世、副業や投資といった手段もありますし、不用品の売却、物の転売というような手法もあります。
「今の仕事してても給料あがらん~」と不平不満を口にするより、具体的な増収策を考える方が建設的です。

また、「費用対効果」や自分の「時給」を意識していきましょう。
スーパーマーケットで数十円単位の節約より、大きな固定費の削減や、単発的な時間労働(例えばUber Eats の配達)の方が、効果的です。

そして、自分の無形の財産=技術・スキルを鍛えていきましょう。
もし、なにかしらのトラブルや転機(リストラや倒産等)が起きたとしても、自分で自分の人生を立て直していけます。
これは「将来への不安」というストレス対策にもなります。

対「健康」のストレス
「健康にいいこと」をするより、「不健康なこと」をやめるように心がけましょう。

「健康にいいことをする」のは、非常に重要ですし、効果的です。
ですが、「食事」に「運動」、「睡眠」や「ストレス発散方法」と気をつけていくのはキリがありません。
人間、やれることには限りがあります。

そこで、「不健康なことはやらない」と、考え方を変えてみましょう。
「寝だめ」「夜更かし」「過食」「食べない・無理なダイエット」「深夜帯の食事」「深酒」「喫煙」・・・
今の生活からの「引き算」から、まずは取り組んでみてはいかがでしょうか。

その「引き算」の取り組みがペースに乗ってくれば、「健康にいいこと」も加えていく余裕というか意識が芽生えていきますよ。

また、仕事や人間関係のストレスから「うつ病」になる人も増えています。
著者も、その経験があり、その体験を機に「ストレスを感じなくて済む考え方=本書の内容」にたどり着きました。
この「うつ」から回復する方法として著者が体得したのが「とにかく外で走ること」でした。
ジョギングでもランニングでもいいのです。
「走りながら『うつうつとした考え』はできない」そうです。
走りすぎも体によくありませんが、ストレスが溜まって、あれこれ考えるようになったときは、肉体的に走り出してみてくださいね。
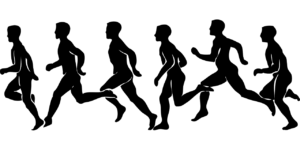
対「夢の実現に向けた」ストレス
人間、誰しも「夢」を持っている・持っていたのではないでしょうか。
その「夢」は、そもそも「かなうもの」か「かなわないもの」なのか。

著者曰く、「夢はかなうもの」と考えている人しか、夢はかなえられないそうです。
なぜなら、「夢は夢でしかない」と考えている人は、すでにして諦めているからです。

そして、「大きな夢」は一人では叶わないそうです。
夢が大きければ、大きいほど、そういえるとのことです。

人の悪口やネガティブワードをやめて、周囲との人間関係を構築して支えてもらいましょう。
時には、自分の責任から逃げず、ごまかさず、謝ることも大切です。
そうした姿勢は、周囲も見ています。

志を同じで、仲良くなりたい人がいれば、一緒に食事をするなりアクティブに動きましょう。
成功者になるには、成功者の輪に入ることも重要なことです。

欲しいものも、欲しいといいましょう。
言いにくいときは「○○さんが欲しいと言っていた」と言ってもいいんです(笑)

また、夢に向かって1回失敗しても、そこで「すべてが終わり」ではないのです。
人生は、死ななかったら「何度でもチャレンジしていい」と考えてみてはどうでしょうか。
本当に望むのなら、何度でもチャレンジしていけば、見えてくる道もあるかもしれません。

おわりに
「ストレスレスの授業(レッスン)」について、ご紹介してきました。
いかがだったでしょうか。
ブログ主が重要と思った事項についてピックアップして記事にしてみました。
「起きた事象は1つだが、視点次第では、幾通りの解釈が成り立つ」
「そうであれば、自分のいいように・役に立つように解釈しよう」
本書を読了した時、そういったメッセージを受け取った気がしました。
あまりにも「恣意的な見方」をしないように気をつける必要はあると思いますが、このストレスフルな現代社会を生きるには、そうした考え方が必要なのではないでしょうか。
ここまでの御高覧、ありがとうございました!
関連記事(関連書籍)
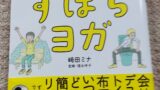
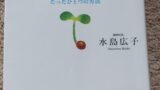




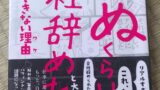
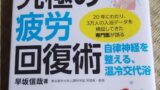

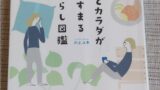

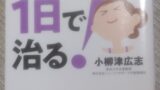

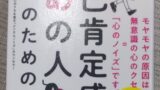
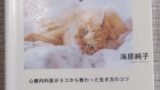
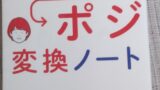
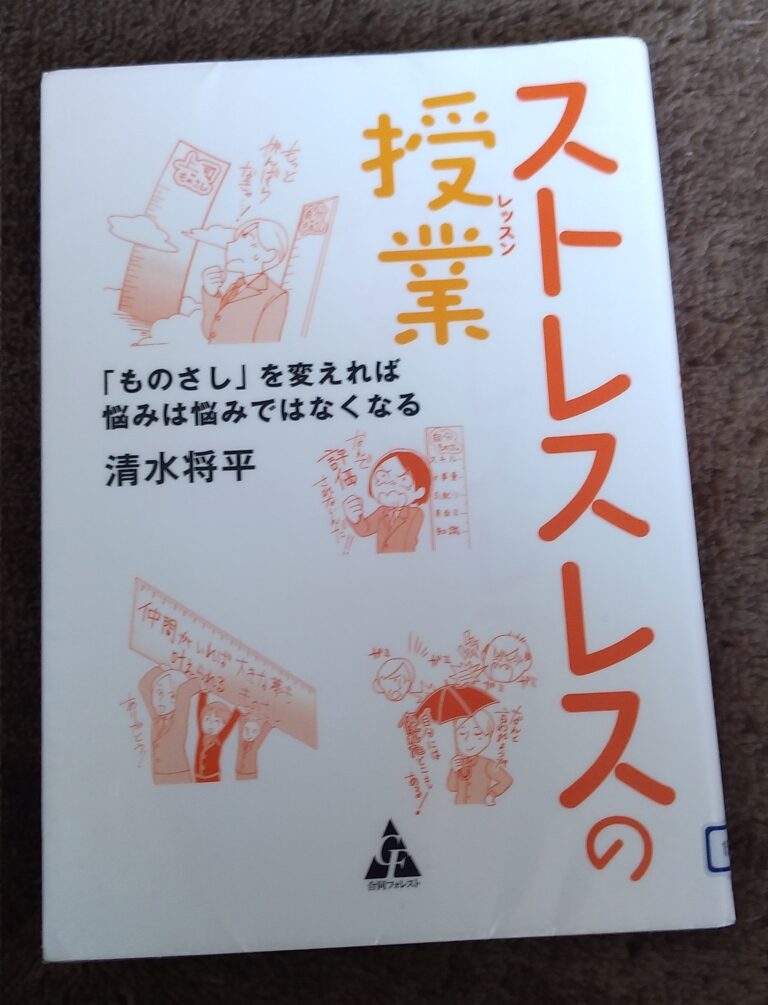
コメント