約2年半前、このブログで「つみたてNISA」のことについてふれました。
その後、今もNISAでの投資を続けています。

さて、今回お送りするのは、NISAに関するブログ主の経験談です。
一見、お得な話にも落とし穴がある……というお話です。
最初に結論を
この記事でお伝えしたいこと。
それは、「投資に関する条件やコストは確認しよう」ということです。
そのことをブログ主が再認識したエピソードを、次項でご紹介します。
投資条件確認の重要性を感じたエピソード
2年半前から、つみたてNISA(現:NISAつみたて投資枠)をはじめたブログ主。
いろいろ試した結果、今は月1万円ほど投資しています。
この投資は、2年前に無職になっても貯金を切り崩して続けました。

その後、ベンチャー企業に再就職。
勤続が1年を超えて、会社から「福利厚生の1つが使えるようになった」と伝えられました。
それが、「NISA奨励制度」
勤続年数に応じて、月ごとにNISAへの投資補助金が会社から出るというもの。
最初は月3千円から。

給与からの天引きではなく、純粋な所得増。
お得な制度!、、と思ったのですが、この制度利用には1つ条件がありました。
それが「会社のメインバンクのローカルバンクの取扱商品に投資すること」。
これが引っ掛かり、ブログ主は制度を利用しないことにしました。
よくよく調べてみたら、ブログ主としては「お得な制度」ではなかったからです。
それでは、「お得そうな制度の落とし穴」がどこだったかを次項で紹介します。

どこが制度の落とし穴だったのか?
「給料に加えて、投資の原資が支給される」
これだけを見ると、お得な制度です。
しかし、世の中はケースバイケース。
ブログ主のケースでは、お得になりませんでした。
では、その理由をご紹介。

まず、会社の制度検討前のブログ主の投資状況。
| 投資歴 | 2年半 | |
| 証券会社 | 楽天証券(ネット証券) | |
| 投資商品 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 月投資5,000円 |
| eMAXIS Slim 米国株式(オールカントリー) | 月投資5,000円 | |
さて、会社の制度で利用可能になる条件がこちら。
| 証券会社 | 窓口:ローカルバンク(銀行) 運用:野村証券(ネット証券) | |
| 投資商品 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 継続して投資可能 |
| eMAXIS Slim 米国株式(オールカントリー) | ||
| 投資額 | 月3,000円。ただし、自己資金による増額は可能 |
|
なお、前提条件として……
・NISAは1つの銀行or証券会社でしか取り扱えない
・そのため、上記の場合、楽天証券→ローカルバンクに取り扱い先を移動する必要あり

さて、会社の制度を利用する場合、投資窓口の会社変更が必須になります。
ここに、大きな落とし穴がありました。
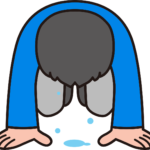
簡単に言うと、今まで証券会社1社だけで投資ができていたのが、関係会社が2社に増えます。
証券会社や銀行は、手数料で飯を食っています。
すなわち、投資に関与する会社が増えると、手数料が多く取られます。

事実、ローカルバンクのHPを確認すると、証券会社の手数料と別に手数料がかかるとあります。
その1つに、保有財産の1.65%(税込)が年間の運用管理料とされていました。
現在のブログ主の保有財産(=すでに投資して得た金額)を考えると……
ローカルバンクに支払う手数料は、約25,000円!
会社からの年間支給額は、36,000円(=3,000円×12カ月)
11,000円が黒字になる計算ではありますが、投資財産を現金に換金する際もローカルバンクに別途手数料がかかります。
今後、(大暴落しなければ)投資額は膨らみますので、手数料の想定額も膨れていきます。

投資の原資が増えるのは結構なんですが、、、
ネット証券会社から銀行に鞍替えすることに、お得感はないんですよね……
おわりに
お得そうな制度も、ふたを開けると……そうでもない、ということについてご紹介しました。
会社の制度は、初めてNISA制度を試してみる人にはお得ですね。
会社がNISAの資金を出してくれ、投資の世界を体験できますから。
ただ、今まで投資していたブログ主には合わなかった、のです。
制度設計って難しいですね。
そして、投資は条件の確認・コストの試算が重要なことを再認識しました。
ここまでのご高覧、ありがとうございました!
関連記事(投資信託)


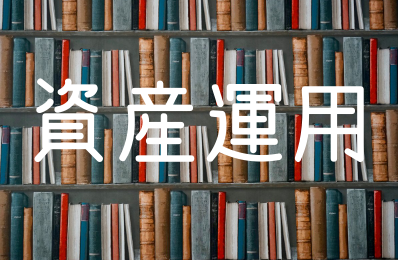
コメント