ブログ主は、名言を知ることが好きですし、SNSで発信してたりします。
このことと人に言うと、「なんか意識高い。苦手」と言われることも……
確かに、名言という言葉から連想するのは「お説教」。
教訓めいた、上から目線のような言葉に聞こえるかもしれません。
「はいはい、そうですね」と心の中で軽く流してしまう人も多いでしょう。
けれど、そんな“説教臭い”言葉こそ、実は私たちが見失っていた視点や行動のヒントを与えてくれると信じています。
この記事では、そんな「名言の効能」について、少し触れていきます。
名言の「説教臭さ」が生まれる理由
そもそも、なぜ名言は説教臭く感じられるのでしょうか?
考えられることの1つに、「言い切り口調である」ことがあります。
たとえば……
「他人と比べるな、過去の自分と比べよ」 経営学者・野田一夫
という言葉は、それ自体が正論ですが、「それができないから困ってるんだよ」と思う人にとっては、机上の空論のように感じられます。
このことから、「現実を知らずに言ってるんじゃないか?」という反発も生まれやすいのです。
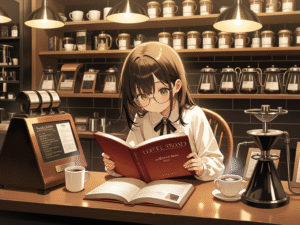
また、言葉がシンプルに凝縮されているため、「状況や背景を省かれている誤解されやすい」こともあります。
このことも、読み手の「現状にフィットしていない」と感じられる原因となります。
さらに、「難しい言い回し・表現」もあったりします。
これは名言の出典が、古い書物だったり、歴史の人物の言葉だったりするからです。
国語の授業やテストを思い出して、聞く気にならなくなるかもしれません。
名言の「説教臭い原因」を3つ挙げてみました。
名言好きのブログ主でも「そうだよな……」と感じていることです。
しかし、それでもなお、「名言が残る・広がる」のは、それなりの理由があるのです。

名言が「役に立つ」3つの理由
自分の状態を映す「鏡」になる
名言は、それを受け取る自分の心の状態によって、意味が変わって見えることがあります。
これは、さきほどの「説教臭さの原因」の裏返しです。
「愛は、愛されるより、愛することにある」 古代ギリシャの哲学者・アリストテレス
たとえば、失恋した直後にこの言葉を目にすると、どこか皮肉に感じるかもしれません。
しかし、数か月後に冷静さを取り戻して読み返したとき、「ああ、自分はただ愛されたいばかりで、与えることを忘れてたな」と、納得が生まれることがあります。
つまり名言は、心の状態によって受け取り方が変わる“心の鏡”なのです。

「本質」を思い出させてくれる
人間は、複雑な問題に直面すると、つい頭が混乱して本質を見失いがちです。
そんなとき、名言のように端的で力強い言葉が、本質を思い出させてくれます。
たとえば、仕事で大きなトラブルが起きて「どうしたら解決できるかな」と悩んでいたときに
「私に世界を救うための時間が1時間だけ与えられたとしたら、最初の55分を何が問題かを発見するために費やし、残りの5分でその問題を解決するだろう」 科学者・アインシュタイン
という言葉にふれ、トラブルに向き直せたことがあります。
名言は誰かからの説教ではなく、自分自身の「立ち戻る場所」を示してくれる役割を果たしてくれたのです。
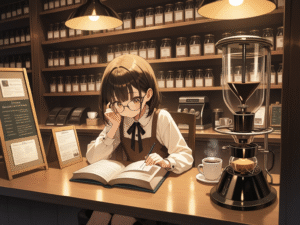
迷ったときの“軸”になる
人は選択に迷ったとき、「他人の意見」に頼りたくなります。
しかし、あれこれ他人に聞きすぎると余計に混乱し、「結局どうすればいいの?」と立ち止まってしまいます。
そんなときに、名言が“自分の判断軸”として機能することがあります。
たとえば、
「今日が人生最後の日だとしたら、私は今やろうとしていることを本当にやりたいと思うだろうか?」 apple創業者・スティーブ・ジョブズ
この言葉は、やるべきかやらざるべきかで迷っているときに、自分の「本音」を呼び起こす強烈な言葉です。
自分の価値観にあった名言を知ることは、選択の基準を外に委ねず、自分の中に取り戻すためのツールとも言えるのです。

名言との付き合い方
名言は、受け取り方を間違えると「自分を責める材料」になってしまう危険もあります。
名言を残した人は、いろいろな時代に実績を残した人ですし、ある種の「正論」だからです。
「できない自分はダメだ」と、自分を追い込んでしまう人もいます。
でも、それは名言に支配されている状態であって、本来の使い方とは違います。
名言とは、あくまで「考えるためのきっかけ」です。
自分にフィットするものを選び、都合よく使っていいのです。
-
ピンと来ない言葉は無理に取り入れない
-
しっくりくる名言だけを「自分のマイ名言」としてストックする
-
落ち込んだときだけ読み返してみる
そんな、「ゆるい距離感」で名言と付きあうのが、ちょうどいいのです。
「過ぎたるは、なお及ばざるがごとし」 中国の思想家・孔子
なにごとも行き過ぎはいけません。
名言も、いたずらに信じ過ぎたり、他人に振りかざすものではありません。
自分にとって、そして自分だけに都合よく使っていけばいい、と思います。
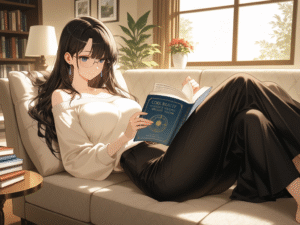
説教臭いけど、やっぱり「残る言葉」には力がある
結局のところ、名言が「説教臭い」のは、それだけ人の心を動かす力があるからだと思います。
先人の人生・経験・知恵が、短い言葉に凝縮されているからこそ、その重みを感じてしまうのです。
私たちは日々、迷い、立ち止まり、悩みながら生きています。
そんなとき、たった一言の言葉が、ふと背中を押してくれることがあります。
それがどれほど“説教臭く”聞こえたとしても――。
その言葉が、自分にとって前に進む助けになるなら、それでいいのです。
そして、繰り返しになりますが、名言の生かし方は、読み手次第です。
「名言? だからなに?」で終わらせてはいけません。
名言は、自分を変えられるただの「きっかけ」にすぎません。
「きっかけ」をどう「結果」につなげるか――
それは、「名言を知った後の自分の行動」にかかっているのです。

コメント